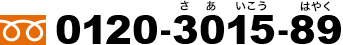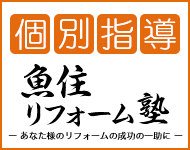当たり前のことで中小企業にはずーっとそれが生命線のごとくつきまとうと思います。
それがうまくいくことが会社の営業に即座に直結します。人数の少ない会社はもろにそれが善くも悪くも表面化することをこの数年で学びました。
今期は新人と言われる人に直接教える時間を前期よりとり、ポイントも考えて教えると同時に、いわゆる所属長というある部署を任せている人たちの、その具体的な役割を教えていくことにも焦点を絞りたいと思っています。
社長という立場はこう、という本ではなく、先日読んだ「課長の会話術」をはじめ、部長とか上司とかいう立場の本を現在いくつか読んでいまして僕もなかなか理解してあげれないところがありますので勉強しています。
ちなみにほとんど読み終えていますが今はこれを読んでいます。非常に分かりやすく、今けっこうこれだと思っています。
「一流の上司二流の上司」吉越浩一郎氏の著書です。
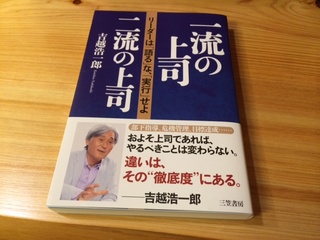
一個の部署を任されたもののしなければいけないことが分かりやすく書いているなと感じています。
僕は自分が良いと感じたものを人に押し付けるところがあります。
もちろん社内に限ってですが、良いと感じた本や文章は社員には読んでほしいと思っています。
今、僕は会社のホワイトボードに日経新聞に連載されている「私の履歴書」を毎日貼っています。他の店にはFAXまでしています。
今月は積水ハウスの社長の書かれているもので、今は天下の積水ハウスかもわかりませんが、昔はこんなことがあった、こんな嬉しいこと、失敗をした。そしてこうやって会社が成長してきたということを書かれています。
ローマは一日にしてならずだと感じましたし、何より「同じやんか」と感じました。
大きく成長できる会社は正しい方向に進み、社会に必要だと感じられた、さまざまな困難に打ち勝ってきた会社であり元々はどこも数人の小さな会社だったはずです。
ということはどこの会社にもそうなれる権利はありますし、夢があります。
「同じやんか」とクレームの話を読んでも感じましたし、非常に勇気をもらえる記事だと、そしてうちの社員の一人でも多くに「同じやんか」と共感してほしくて毎日毎日、台湾に行っている間も柴田に頼み新聞をコンビニで買ってもらい同じように貼って、FAXも送り続けてもらいました。
これが僕の意図なんです。
そして、今日書きたいことは所属長の役割はその僕の意図を彼ら彼女らの言葉に変えて、部下に伝えてほしいということなんです。
それこそが一つの部署を任された人間の仕事の一つだと思いますし、それは意図を理解しているからなしえる仕業だと思うんです。
昨日、赤穂店に行ったら赤穂店のホワイトボードの前にFAXで送っている新聞などが並んでいました。

そこにはその店の人間の印鑑が紙ごとに押されていました。
推測するに、読んだよ〜のサインなんでしょう。
これは僕のさせたことではありませんし、聞いてもいません。
これはこの店を任されている東がおそらく自分の言葉でみんなに話し、こうさせているのかなと思います。
店の営業がうまくいくというのはこういうことだと思います。
会社の意向を理解したうえでその部署に伝える。
これって簡単そうでなかなかできていないことが多いです。
中には会社と所属長との見解が少しずれているときもあるでしょうが、それを表に出さず、いわば自己犠牲をして伝える。
これが上司の力量だと思いますし、これでその部署の部下は迷わないと思います。
難しい立場ですが、僕自身に対しても部下は上司を選べません。部下を活かすも殺すも、伸ばすも停滞させるも上司次第。
そう思ったらやりがいのあるポジションですよね!